
|
こうした膨大な被害に加えて、電話の不通や交通の途絶など悪条件が重なるから、いままでのシステムだけでは情報収集に相当の時間を要するにちがいない。 そこで、大都市震災では新たな情報収集システムが必要になる。そのようなシステムとして、たとえばヘリコプターによる包括的・機動的情報収集(今回の震災ではこのことが大いに議論された)や、高所監視カメラなどニューメディアの導入(その耐震性の強化も必要)、受持ち区域を決めて消防団員や自主防災組織に情報収集を分担させること(その前提として自主防災組織の強化が必要)などがおそらく有効であろう。さらに、基本的には警察・消防などの防災機関がそれぞれ独自の情報収集システムを構築することが重要だが、防災機関同士の横の連絡も災害時には不可欠であり、こうした連絡用として、たとえば地域防災無線の導入なども考える必要があろう。この地域防災無線は、市町村・警察・消防などの防災機関と、医療・電気・ガス・水道・交通・デパート・劇場などの機関を結ぶ無線網であり、いままでせいぜい電話に頼るしかなかったこれら機関のあいだの相互連絡を可能にする、という意味で画期的なものである(図3)。現在これを導入している市町村は決して多くなく、東京23区で10区程度、静岡県で7−8市町村程度の普及率だというが、このシステムは、適切な運用マニュアルが整備されれば、大都市災害時における情報収集システムとしてきわめて有望なものである。 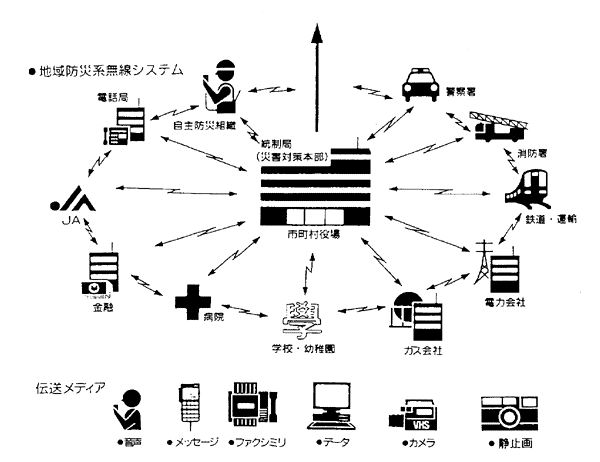
図3地域防災無線の概念
前ページ 目次へ 次ページ
|

|